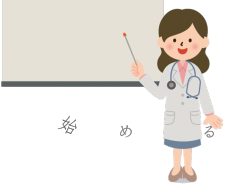- Home
- 付録 事故に遭遇した場合
付録 事故に遭遇した場合
- 付録 事故に遭遇した場合 はコメントを受け付けていません
同乗者がいた場合は同乗者が事故対応の主導者になります。運転手が仕切り屋で経験豊富だった場合は、尊重して影の事故対応主導者になってください。運転手が長くペーパードライバーだったような場合は、何をすべきかわからないことがほとんどです。状況に即して無理のない役割を指示してあげましょう。
主導者は、正しい状況判断、正しい情報、手順の確認、やり忘れの確認、定期的な状況報告などをコントロールしてください。負傷者がいる場合は、真っ先に救助します。ただし二次災害が起きないように、というのがポイントです。心情的には負傷者優先となりますが、二次災害が起きてしまうと、また新たな悲劇が生まれます。周囲の状況を判断し、可能であれば二次災害が起きないようにして、負傷者の保護・救助を行いましょう。
●二次災害の回避
事故現場は保存しておく必要があり、車も移動してはいけない場合があります。事故者の心情として事故車を路肩に寄せるなどの対応をしてしまいがちですが、一時的な渋滞の心配よりも負傷者保護、二次災害の回避、さらに事故現場の保存を優先することが重要です。それらを考慮したうえで、問題がなければ路肩に寄せるなどの対応をしましょう。
まずは三角停止表示版、発煙筒などで事故が起きたことを周囲にアピールします。その後、道路に散乱した細かい部品などを安全な場所にまとめるなどの対応をしたほうがよいでしょう。部品や事故車を移動する前に、念のために事故現場を写真に撮りためましょう。事故現場の周辺と、日時がわかるもの、車種が特定できるもの、相手を特定できるものなども記録しておくとよいでしょう。可能なら車検証、免許証などなどです。
●通報、連絡
負傷者がいる場合は消防署に通報し救急車を要請しましょう。次に警察への連絡です。事故現場(場所)と事故の状況、負傷者のあるなし等を伝えます。事故を起こした瞬間は、一瞬頭がまっ白になってパニックになりますが、あせらずにひと呼吸おいて冷静に状況を伝えてください。
ちなみに消防署に交通事故として連絡した場合は、消防署側で警察に報告が入る仕組みがあるようです。反対に警察に連絡した場合は、警察署は救急車要請の必要性の有無を確認してくれます。通常は救急車の要請が先ですが、もらい事故の場合(当て逃げ、ひき逃げなど)の場合は警察の連絡も急務ですね。
次に、加入している保険会社に連絡します。基本は運転手の加入しているへの保険会社への連絡です。運転手がペーパードライバーなどで自ら保険に加入していない場合は、車の所有者の保険会社に連絡します。加入している保険のオプションにより保険が適用されない場合もあるので、オプションを今一度確認しましょう。
事故を起こした場合は人身事故・物損事故にかかわらず、必ず警察に報告する義務があります。特に単独事故は「相手がいないから大丈夫」という理由で報告を怠る人もいますが、警察に届け出を出して「交通事故証明書」を発行してもらわないと修理等の保険金も出ませんし、相手がある場合は後日の示談交渉にも支障が生じます。また警察への報告義務に違反した場合、罰則もあるので注意しましょう。
レッカー移動などの対応が必要な場合に備え、他の事故対応サービス(例:JAF)にも連絡します。
事故への初期対応が滞りなく進められたら、今後起こりうること、やるべきことへの対応を考えます。代車、代行運転手、レッカー車、宅急便などの手配、自宅や親戚などへの連絡、被害者への連絡、会社への連絡・対応などなどです。
●事故を起こしたときの対応のポイント
- 負傷者の有無
- 二次災害の回避
- 事故現場の保存
- 救急車要請の必要性の有無
- 警察への通報
- 保険会社への連絡
- その他連絡先の確認
- 「今後の対応」への対応
- 反省と次回への対応