老猫・高齢猫との暮らし【健康体操】
めでたく歩行困難からの復活を遂げた我が家のうち猫ですが、高齢なことに変わりはなく予断は許しません。
引き続き、健康管理と健康体操を続けようと思います。
その中で一番効果的と思われたのは「腹上寝!」、以外と人の体の上で寝るのってバランスが必要で大変なようです。
ゆったりとした猫時間の中で、ゆっくりと機能が回復して行ってくれるような気がしました。
そして、病気のサインと老化のサインと個性のサインとを正しく見分けてあげることが大切と思いました。
老化と退化と進化の幼児化の区別
老化現象が現れたからといって、その全てが回復不能の「不治の老化」ということではないでしょう。
同じ老化現象に区分されていても機能が劣化や消滅してしまって、もう元には戻らないものと、単に運動不足や環境への適応で現れた症状や特徴が高齢猫にはよく見られるということかもしれません。
元に戻らないものへの高望みは負担が増えるだけで良いことではありませんが、元に戻るものを放置してしまうのは勿体無いし、後悔の元になりかねません。
環境や個体差でその症状は様々なパターンで現れることでしょう。
とりあえず我が家の猫、そのいわゆる老化現象について観察してみましたので参考にしてください。
我が家の、猫人生のうちの半分以上、実に半生が老猫と区分される二十歳すぎの高齢猫のお話です。※
先日しでかした(寝たきり猫のベッドの屋根は取り払おう)事件であわや寝たきり待遇にしてしまいそうになったことへのプチ反省も兼ねてのお詫びでもあります。
危うく回復してしまうことができるはずだった症状を、放置してしまい、必要以上に老化を進めてしまうところだったのです。
参照:廃用症候群
それでも治るからといって、薬漬けや、無理やりリハビリさせるのも、考えものです。
猫は自分のことをよくわかっているし、好き勝手に生きていることこそが猫の証だ。という考えも尊重すべきです。
長く生きさえすれば幸せだったということではないでしょうから。
放置と適度な介護と、過度な保護とのそれぞれで、一番後悔しない方法をご選択ください。
猫における老化と幼児化と退化と進化の区別
用語が紛らわしいので、猫における変化や状態の呼び名とそれぞれの特徴を定義しておきます。
-
老化:
猫の人生の終わりの方で現れる体の劣化による症状うち、回復不能な状態・症状
-
幼児化・退行
幼児・子供の頃に戻る事、猫を撫でると猫がゴロゴロいうときの状態や、猫なで声を出しているときの飼い主の状態
なでたり、心臓の音を聞いたり、首根っこをつかまれたりしているときは幼児の時を思い出してご機嫌になると言われている。
成人した猫をあまりにも可愛がりすぎると、幼児の頃の性格に戻ってしまう場合があります。
-
進化:
必要な機能が追加されたり高性能になること、あるいはいらない機能を捨て去ること。
猫は猫なりに、生活していく上で、必要なことと、不要なものを区別し、その結果、新しい機能が恒久的に備わったり、不要な機能を恒久的に使わなくなったりするわけです。その場合はたとえ見た目は老化でも実際には何も心配する必要はありません。
-
劣化:
備わっている機能のパフォーマンスが落ちる事
怪我とか病気とかで、年齢とは関係ない、出来事が原因の症状のことです。
-
退化:
進歩がとまって、以前の状態にもどること。あともどり。
実際には、文脈依存度大で、進化も退行も退化と呼ばれるなど意味を特定しにくいことが多い。
ここでは進化した結果機能が退化する生物学的な意味の退化は省き、退行のことと定義しておきます。
-
学習・慣れ:
環境に適応しているだけで体には変化が生じていないときの事
木に登る必要がなければ、その筋力が落ちるのは仕方がありません。
或る日突然「もう木に登ることはない」と気がつくことは老化ではなく学習だったり、知恵がついたという状態です。
こういうのもありますね
代表的な老化現象
代表的な老化現象について良くまとめられているallaboutさんから引用させていただきました。
(付け加えた項目もあります)
症状
- セルフグルーミングの回数が減って、毛艶や毛量が減ってくる
- 口や舌や色素の薄い内膜にシミが出てくる
- 黒猫など色の濃い猫の顔まわりに白髪が目立ってくる
- 瞬発力が衰え、あまり動かなくなってくる
- 筋肉が衰え、痩せてきて、お腹が垂れてくる
- 歯が弱ってくる
- 爪の伸びが遅くなる
- 体温管理機能が落ちてくるので寒さに弱くなる
- 痩せてくる
- 夜泣き
- 爪が戻らなくなる
- 食欲不振
- 髭が伸びる
- 肉球が滑る
対策
- 猫の体調変化に注意する
- 食べやすい食事を与える
- トイレや寝床の位置に気配りを
- 遊びに誘う
- 積極的に猫を触る
- 美容にも気を使う
主な疾患
- 腎臓疾患
- 肝臓疾患
- ガン(腫瘍)
- 糖尿病
- 高血圧
- 尿石症
- 歯周病(歯槽膿漏)
- 口内炎
- 甲状腺機能亢進症
- 便秘
- 認知症
- 狼瘡様爪床炎
それではうちの猫の現状をお伝えします。
うちの高齢猫の場合
生い立ち
現れる症状は環境により大きく異なると思われるので、簡単に生い立ちを書いておきます。
性別指名
生い立ち
- 捨て猫
- DV猫(いじめられる方)
かなり臆病になってしまったと思います
- 引っ越し
私が譲り受けました
- 避妊手術
- 多頭飼い
野良猫が出入りする家で、主人(ボス猫)にかこわれました
- 主人との決別
この時期から寂しさからかさらに泣きわめくようになりました。
- 引っ越し
うるさすぎて苦情が来るので、ペットOKのマンションに引っ越し
- 引きこもり
引き込こもり先は浴室に落ち着き、以降浴室住まい(なぜか浴室に個室がある)
- 落ちこもり
最近高所へのジャンプに失敗しまくり、落ち込んでしまい、少しの段差でも躊躇するようになってしまいました。
自信を持ってジャンプ(のり上げ)できるお気に入りのアイテムは、閉じたマックブックエアー
- 健康今までに病院にかかったことはありません。
クリニックに行ったのは避妊手術の時のみです。
うち猫の場合
先の症状をうち猫的に当てはめてみました。
老猫の場合は【老】そうでない場合は、単なる年の場合は【高】、その他の場合はその理由を書き加えます。
症状
- 【高】セルフグルーミングの回数が減って、毛艶や毛量が減ってくる
グルーミングの回数と、艶や量とかが対応していないように思います。
うち猫は、グルーミングの回数は昔から少なく、美味しくご飯を食べた時だけでした。
艶は活動量の差な気がします。
毛量はうちの猫は昨年(二十歳)あたりから確かに毛の伸びが遅くなって、昨年の虎狩りが治りません。
しかし若ハゲのに悩む人に面と向かって老化とは言いませんよね。
- 【老】口や舌や色素の薄い内膜にシミが出てくる
- 黒猫など色の濃い猫の顔まわりに白髪が目立ってくる
うち猫に昔と今で白黒加減に変化はありません。
ただし実験のため黒ぶちの箇所の毛を刈った後には真っ白に変わった箇所と、一旦白くなったにもかかわらずまた黒くなった箇所もあり。
- 【老】瞬発力が衰え、あまり動かなくなってくる
瞬発力というより、視力や聴力の衰えや、そもそも意識朦朧を心配してあげましょう。
- 【高】筋肉が衰え、痩せてきて、お腹が垂れてくる
病気の時は痩せますが治ると元に戻ると思います。
うち猫は二歳の時に膨れ上がったお腹が痩せた後に垂れ下がり、以来ずっと垂れ下がったままです。
が、最近肉が詰まってきました。
お腹のタレより、背中の戻り加減で脱水加減を確認するのが正しいと思います。
- 【高】歯が弱ってくる
- 【老】爪の伸びが遅くなる
- 【老】体温管理機能が落ちてくるので寒さに弱くなる
- 痩せてくる
老化より、虫歯や、病気の心配をした方が良いでしょう
- 夜泣き
うち猫は寂しさから幼児の時から夜泣き全開です。
ところがこんな事件も、寂しいのと温かいのとで私の長年愛用のセーターをベッドに差し入れしてあげたところ、その日から1時間おきに夜泣きが・・・返ってって寂しくなってしまったのかとも思ったのですがそのセーターを捨てたところ、いきなり爆睡・・・臭かったようです。
- 【高】爪が戻らなくなる
後ろ足の爪が確かに戻らなくて出っぱなしになっていたのですが、肉球プニプニと爪を押し込なだり、爪割をしてあげていたところ、元に戻りました。
それよりも、生活の中に爪を使う場面が少ないので、爪を使う場面が「爪とぎ」ぐらいになってしまっているので、爪とぎでとがない爪が、ノーメンテになってしまうことが問題になります。
なので爪とぎをしているしていないにかかわらず爪の状態の確認が必要です。
そしてつめの脱皮がうまくいってない時には、爪切り、あるいは人の爪で割ってあげることが必要です。
また爪が全部とれてしまう「狼瘡様爪床炎(ろうそうようそうしょうえん)」という病気のチェックもします。 狼瘡様爪床炎 « 厚別中央通どうぶつ病院
- 【高】喋り出した!
長く生きていると、言葉?のバリエーションが増えてきて、一人でむにゃむにゃ喋りながら何かしている時があります。
強めに撫でても吐き出す息で、グーとかフンとか言います。
- 【高】髭が伸びる
視力が落ちたり、意識が朦朧としてくると、急激にヒゲが伸びてきます。やはりセンサーとして活用しているのでしょう。
そして、回復すると通常の長さに戻ります。
うち猫は現在右ヒゲが長く、左ヒゲは通常サイズです。右側がよく見えていないのかもしれません。
- 【老】肉球が滑るようになる。
肉球の乾燥も老化現象だそうです。
うち猫はフローリングに立っていられない時もあります。
きっとジャンプに失敗しだした一因でもあったことでしょう。
犬用の滑り止めクリームが良さそうです。
我が家では人用のハンドクリームで毒性の少ないNIVEAを使っています。
トイレをするたびに白くなってしまうのかと心配でしたが杞憂でした。
対策
- 猫の体調変化に注意する
- 食べやすい食事を与える
- トイレや寝床の位置に気配りを
- 遊びに誘う
- 積極的に猫を触る
その通りですね。
これに後述の健康体操をつけくわたいと思います。
主な疾患
疾患についても、余計なことは言わない方が良さそうなので控えます。
ただ、年齢と関係なく、健康的な生活を取り戻せば回復してしまう症状が多々あると思われます。
自分に当てはめて考えると
総じて、見た目の老化に気がついたら、それからでも遅くないので、視力の状態、聴力の状態、歯の状態、風邪などの病気、脱水加減。骨折などの外傷、病気や高齢のために意識が朦朧としている、など見た目と別の根本原因があるかどうか確認してあげるほうが先決ですね。
そう思うとやはり、病院に連れて行ったほうが早そうですね。
しかしうち猫は、クリニックに連れて行くと寿命が10年ぐらい縮まりそうなので連れて行きません。
我が家の健康体操とメンテナンス
おしくらまんじゅう
手のひらで顔を前から覆ってそのまま前に押します。
正常であればすぐに抵抗すると思います。
どのような場面でも大抵押されて後ろに下がらないように抵抗します。
押すたびに踏ん張るために爪が出し入れします。
瞬発力と、筋力と、爪の体操になるでしょう
爪切り
年と関係なく、爪とぎだけでは、研がれない爪があるので定期的に見てあげましょう。
そして爪とぎできていない爪は、爪を切ったり、代わり爪切りや人間の爪で猫爪を割ってあげて爪の脱皮を手伝いましょう。
合わせて肉球プニプニをしてあげれば、爪の出し入れにも効果的です。
ついでに滑り止めのために肉球にハンドクリーム(NIVEA)を塗ってあげています。
ハンドクリームは滑り止めには効果絶大ですし、汚れが付着するかと思いきや逆に以前より綺麗に保てています。
うち猫はとうの昔に顔も滅多に洗わないし、爪噛みもしないし肉球などほとんどなめてはいないでしょう。
毒性が少ないNIVEAを使っていますが、猫にαリポ酸はよくないと言われているのでハンドクリーム全てが良いようではないです。
毒性とか気になるのでしたら犬猫用のものを購入すると良いと思います。
クリニックでお伺いしてみると良いでしょう。
マッサージ
グルーミングに合わせて、全身くまなく様々な箇所をつまんでみたり撫でてみたりしましょう。
痛いところがあればそこでわかります。
つまむことで、脱水加減がわかります。
せんべい返し
決まった方向にしか寝なくなったりするので、横に寝ているときには定期的にひっくり返してあげましょう。
変な癖が取れるかもしれません。
せんべい返しは耳掃除のときには必須の技です。
横蹴り
グルーミングの際に猫が横になったときに横蹴り?させます。
頭からお尻にグルーミングやなで降ろし、寝ている猫が床を滑ってしまうぐらいに、強力にします。
そしてその時の後ろ足が壁や障害物で反発できるような位置で行うと足腰の運動になります。
押さえ込み
同じくグルーミングやなでおろしを上からグイグイ押さえ込みながら行います。
猫は押さえると伸びて、引っ張ると縮むという、とっても解りやすく素直じゃありません。
この性格を活かして、伸ばしたいときには縮めて、縮めたいときには押すと簡単に思い通りになります。
着地
首根っこつまみを行い手足が地面から離れたら、掴んだ手を離して、猫に着地させます。
首根っこだけでなく、お尻もつかめば、任意の高さと体制から着地の体操ができます。
高さは足腰の強さや、元気度に合わせて行います。
登山
仰向けに寝て、猫に登山をさせます。
飼い主より高い位置から見下ろすことはかなりご機嫌な行為なはずです。
人のからは思ったより安定しないので、足腰の強化と、バランス能力は格段に上がると思います。
飛び越えることや、後ろ足がきちんと障害物を避けるか、がポイントです。
水分補給
体操を行っている間でもいつでも水を飲めるように用意しておきましょう。
いつもと違う場所に水を用意した場合には、そこにあるのが水であることがわかるようにしてあげます。
視力が弱っているときの頼りは匂いだと思うので新鮮な水、あるいはだし入りの水などで、水であることをわかりやすくしてあげることが必要かもしれません。
トイレ休憩
健康体操に付き合ってくれなくなったとしても興味が失せたのではなく、トイレに行きたい場合もありますので、休憩を挟みましょう
指差し確認
人差し指の匂いを嗅いでもらいます。
目的は近距離に目のピントを合わせる練習です。
色々なパターンで匂いを嗅いでもらいます。
指の指し方は大きく分けて三種類あります。
一つは指した指を動かさないで、猫が指をめがけて近づいてくるパターン。
これで距離感をつかむことができるようになります。
特に後ろ足の足取りはこの事前に見た風景を元に距離感をつかんでいると思うので、この体操?は重要だと思います。
二つ目は指を遠くから眉間に抜けて近づけていきます。
これで近いところを見る練習になるでしょう。
三つ目は猫じゃらしのように動かします。
何かを見る練習として、ゆっくりでもいいので、見てくれるようにします。
洗顔
目やに、耳垢はもちろんですが、鼻ガミと歯磨きは丁寧にしてあげましょう。
水も飲んでくれない時に鼻ガミすると、飲んでくれたりします。
食欲がないのではなく、匂いが分からなかったのでしょう。そういうときは食事もしてくれます。
同様にが磨きも(うちはティシュで牙だけ適当に)虫歯の発見になります。
洗顔は、痛がって手(前足)で払いのけられるまでやってます。
片手立ちのバランスの練習になるからです。
散歩
うち猫は外出はできないのでベランダでお散歩させています。
ビビリーなので完全に腰抜け歩きになります。
室内とは異なる臭いがするのか、鼻をヒクヒクさせて落ち着きなくウロウロしています。
それでも足腰のリハビリに一番で普通に歩くようになっていくのが目にとれます。
その他
その他それそれの好みとかで今まで通りの遊びを試してみます。
※医学的に根拠のない話も含まれているかもしれないので、自己責任でお願いします。とりあえずすべてをそのまま信用しないでください。

追記です。
書き直し:我が家の猫の老け具合
分類して、整理して書けばわかりやすく伝わるかと思ったのですが、読み直してみたところ、逆に伝わっていないことが判明したので、
改めて我が家の猫の老け具合と考察を1行で書いてみます。
2回目の引越し先の今の我が家には爪が必要な布成分がほとんどない洋室風で構成されています。
したがってジャンプするためには爪ではなく肉球のグリップ力に頼らざるをえません。
この肉球が最近多分十九歳ぐらいの頃にグリップ力が落ちてきた結果、ジャンプに失敗するようになったと思います。
このグリップ力の低下は日増しに進み、最近では、なんと前足が滑ってフローリングに立っていられない時もあります。
多分同じ十九歳くらいの時期に視力も落ちてきたようで、気がついたら食事や、水分補給の時にえさを見ながら食べるのではなく、匂いを頼りにして舌をペロペロしてみるようになっていました。
特に水道の蛇口から飲む時には、いつまでたっても場所が定まらず、有名なバカ猫よろしく、顔にシャワー状態で、おまけに毛の脂分で水を弾くのでなおさら、一向に水を飲めてはいません。
このことで、水分補給の量はかなり激減していると思われ、色々な不調をきたしているのではないかと思われます。
ジャンプできなくなったことへの落胆は、ジャンプを躊躇しているときの迷いの表情から大きいと読み取れます。
そのせいで、行動する時間が減り、寝る時間が少なくなっていきたと思われます。
これはほとんど生きる理由がなくなったのと等しいのではないでしょうか。
寝起きが悪いどころか、目を完全に覚ます必要すらないのです。
傍目には、ボケですね。
なので歩くときにつまずいたりとかの目測の誤りは、体がついてこないこともありますが、視力の低下に加え、脳もきちんと働いていないからなのではないでしょうか?
猫年齢では10歳程度の私も、最近休日の過ごし方が家でゴロゴロなためか、ふらついて歩けない時や、寝起きの悪さは驚くものがあります。
規則正しく健康な日常を送らないと、老猫とか、ボケ老人とか言われてしまうわけですが、生活態度を変えるだけでまだまだいけるのかもしれません。
猫の生活態度は、飼い主の生活態度です。
大抵、飼い主の生活の中で一番楽していたりサボっている部分を真似していると思います。
2月末に後ろ足が動かなくなってから、健康体操を今までよりも積極的に始めて2ヶ月経ちましたが、今では普通に歩けるようになりました。
ジャンプも久しぶりにトライしてみました。見事に撃沈したのは残念ですが、元気になった証拠です。
ただ生きる楽しさはそんなに提供できてはいないので、ボケ加減は全盛期のクリーンな頃には及びません。
これはしょうがないと思っています。
もしかしたら我が家の猫にとって一番楽しかった時期が、毎日違う野良猫に喧嘩を売られビクビクしながら生活していた多頭飼いの頃かもしれないのですから。
参考情報
※猫糞に注意
ネコの糞に含まれる寄生虫で「怒り病」生じる可能性
衝動的に激怒する傾向のある人は、ネコの糞などに含まれる寄生虫に影響されている可能性があることが、米シカゴ大学のEmil Coccaro氏らの研究で示唆された。研究では、間欠性爆発性障害(IED)の患者は、トキソプラズマ症の原因となるトキソプラズマ原虫の保有率が2倍以上高いことが判明したという。
IEDは、頻回かつ衝動的に、状況に釣り合わないほどの言語的・身体的な攻撃性を爆発させる精神疾患の1つ。米国では1,600万人にみられるという。
一方、トキソプラズマ症は、ネコの糞や十分に加熱調理されていない肉の中にみられる寄生虫によって引き起こされる感染症だ。全人類の約3分の1が感染しているといわれ、一般的には感染しても症状は少ない。ただし、新生児や免疫不全患者では重症化リスクが高くなる。
研究では成人358人を対象とし、IED群、IED以外の精神疾患群、精神疾患のない対照群の3群に分けた。トキソプラズマ抗体陽性率は、IED群では22%だったが、対照群ではわずか9%、精神疾患群では約16%だった。攻撃性・衝動性のスコアは、精神疾患群では対照群と同程度だったが、IED群では他の2群よりはるかに高かった。
トキソプラズマ陽性の対象者では、怒り・攻撃性のスコアが有意に高かった。
Coccaro氏は「攻撃性の問題を抱える人は、単なる性格や癖なのではなく、何らかの背景をもつ可能性もある。ただし、本研究は臨床試験でないため、直接的な因果関係は明らかでない。また、トキソプラズマ陽性の人全員が攻撃性の問題を有するわけでもない」と話している。
専門家は、トキソプラズマ症の予防として、調理時は野菜をよく洗い、肉を十分に加熱すること、ネコは屋内で飼育すること、ネコの糞に触れないよう注意することなどを挙げている。研究は「Journal of Clinical Psychiatry」3月23日号に掲載された。
[2016年03月23日/HealthDayNews]Copyright (c) 2016 HealthDay. All rights reserved.
引用元 ケアネット
[csshop service=”rakuten” mode=”embed” keyword=”パナズー パウケアクリーム”]
以上
老猫・高齢猫との暮らし【健康体操】
でした。
老猫・高齢猫との暮らし【猫目線】もお読みいただければ幸いです。

















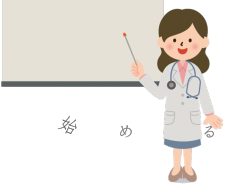
この記事へのコメントはありません。