引きはがすといっても、親子の縁や恋仲の猫を引き離すのではありません。
木にしがみついていたり、キャットタワーでご機嫌だったりする猫を、
そこからご移動願うときの方法です。
前回の、高いところから降りられない猫も、
せっかくはしごで猫を直接抱きかかえられる場面にまでこぎつけたのに、
木から不安定に引き離されることを怖がりしがみついてしまい、
はしごの上で格闘してしまったりします。
同様に、
抱きかかえられることにやぶさかではない猫も、
人の膝や、肩に飛び乗ってご満悦な猫も、
いざ地面に降ろされるときには「ジタバタ」することが多いのではないでしょうか?
この、どちらの場面でも使える技が、首根っことおしり部分をつまむ2点持ちなのですが……
以前に書いていたを思い出しました ⇒「首根っこの持ち方 二点持ち編」
見事にかぶってますが、
着地の際の「ジタバタ」だけではなく、前回の続きでもある、猫ちゃんを救うときにも、にも使えるということでご容赦を。
例えば木の上にいる猫からみたら、「大丈夫だからね」と未知の言語でわめいている人間に体を預ける事には抵抗があります。
おまけに笑いかけているつもりが、猫から見たら般若のごとく喧嘩を売っている顔に見える臨戦体勢のなか、牽制のジャブのように伸びてくる腕…
高いところには限らないかもしれませんが、
今置かれている状況から、信用のおけない第三者の手によって、未知な状態に踏み入れてしまいそうになったら、だれでも抵抗するでしょう。
野性的というより、生き物として当たり前の行動ですね。
それを解決するのが「首根っこ持ち」です。
つまんだ瞬間に<未知の生物>から<信頼のおけるお母さん>に切り替わるのでしょう。
首根っこを持つだけでも、うまくすれば木からはがれてくれます。
まだまだ抵抗があるときには、加えておしりもつまむのです。
理由はわかりませんがさらに<無防備>になってくれます。
一気に引きはがすのがコツですが、爪が引っ掛かったら、一度押し戻して、再度、一気引きはがしを試すとそのうちうまくいきます。
一旦はうまくつままれた場合でもあまりつままれるのが好きではない猫や、つまみ方が悪いときは、地面付近で新たに大暴れする場合があります。
引きはがす時には首根っこだけの一点でもいいですが、地面に降ろす際には2点持ちにすることをお勧めします。
結果的に一点持ちだけの場合には、いっそのこと地面付近で放り投げてしまうほうが、いつまでもつまんでいることによる双方の痛手を軽減することができるかもしれません。
うまくつまめるようになるとケージに入れるときにも、水や餌の皿をひっくり返すこともなくなり、猫にしてもかなりのストレス軽減になるのではないでしょうか。
つまみ方ですが、やはり、たくさん経験を積まれることをお勧めします。
つまむ部分の特定と、勢いが重要だからです。
特に抱いている猫の2点つまみは、結構な難易度です。
まずつまむ側の手の角度がかなりアクロバット的になります。
抱いている状態のまま、首の部分と、おしりの部分を猫に負担のない位置と角度とつまみぐ具合を探ります。
うまくつかめたら、一気につるします。
つるした時の腕の状態がアクロバットすぎて、着地に持っていけないときにはいったんおしり側を離し、改めて着地させやすい角度に持ち直してから、着地させます。
着地させにくいからと言っておしり側を離してしまうと効果は半減です。
抱いている猫をつまめるようになると、<木からひっぺはがした猫>をいったん抱きかかえ、改めて着地の際に<2点持ち>で地面に解放させてあげることができます。
着地のコツとしては猫自身がジャンプした後に着地するような自然な体制とスピードを再現できれば、何事もなく着地できます。
要は猫の思い通りになっていないからじたばたするのです。
ここまでできれば鬼に金棒ですね。
是非ともマスターしておくことをお勧めします。
我が家の、来年成人式を迎えるおめでたな猫は、最近背中の皮下脂肪?が減ってきたようです。
抱いて丸くなっている時のおしり部分のつまみが難しくなってきました。
それでも他の方法に比べれば、はるかにストレスは少ないでしょう。
ストレスだけではなく<母親の愛に包まれている>感があるかもしれません。
長生きの一因になっているかもしれないかもです。
画像なしですいません。
コメント
-
2015年 3月 29日トラックバック:高いところから降りられない猫と やぶへびでやじうまな下僕達
-
2016年 5月 16日トラックバック:首根っこをつかむ(間違いだらけの「猫の首根っこをつかむ」)
















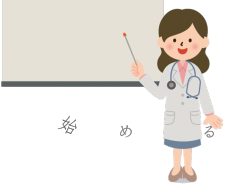
この記事へのコメントはありません。