「安心して同乗してくれる」、「運転がうまいねと褒められる」ための『【いやいや極める】お抱え運転手』。
今回はハンドル操作について紹介します。
ハンドル操作の上手下手は同乗者のみならず、本人が一番気になっていることでもあるでしょう。
本人が気になる点としては以下の様なものが挙げられます。
- 直線でふらつく
- 常にハンドルを動かしている
- カーブでハンドルを切り直す
- 走行ラインが悪い
- ハンドル操作がバタバタする
- 操作中に手が絡まる
- 握る場所が正しいか気になる
まだまだあることでしょう
対して同乗者は別の視点で運転手のハンドル操作を評価しています。
- ふらふらする
- 気持ち悪くなってきた
- 運転手が怖がっている
- 運転手の落ち着きが無い
このように同乗者は、実際に運転しているわけではないことと、運転手に自らの命を預けていることからくる、安心感、不安感がハンドル操作の評価となります。
そこで今回は技術的なハンドル操作ではなく、同乗者に好評価をもらえるような、安心感を与えられるような、ハンドル操作についてご紹介してみます。
本編では小手先ではなく運転手の正しい知識に基づく正当な自信と、それによる同乗者の安心を勝ち得ることを主眼としています。
最初にハンドル操作がふらふらしてしまうことの理由を説明します。
そして理屈を理解した上で、ふらふらしないための運転方法を説明します。
何故直線でふらふらするか
フラフラする理由は様々なところで説明がされているでしょう。
近くを見過ぎるからフラフラするで、なるべく遠くを見て運転しましょう。
これはその通りです。
しかしこれでは運転手が下手くそだと言わんばかりです。
フラフラする理由には視点の位置によるものだけではなく、ハンドルそのものの物理的な特性によるものが含まれています。
まずはハンドルとタイヤとの構造上の精度。
ハンドル操作が実際にタイヤにその操作が伝わるまでには何箇所か接合点があります。
バイクのようにタイヤにハンドルが直結はしていないのです。
接合点には必ず余裕というかガタが存在します。
次に車の構造上の特性
車は真っ直ぐ走るだけではありません。
道路は直線だけではなく、曲がり角もあれば、段差もあります、高速道路もあれば、悪路もあります。
そのために車は、それらの道路を考慮した上でのセッティングが施されます。
さらに、セッティングとは別に、費用面での精度不足からくるガタなどの特性も加えられます。
この接合点のガタと、車の構造上の特性から、ハンドルをたとえまっすぐに固定していても車が真っすぐ進んでくれるとは限らないのです。
最後に道路の特性
特性というか、道路はまっ平らではないということです。
相乗以上に凸凹しているのです。
それらの凸凹がタイヤに伝わり、車の特性による反応の結果フラフラすることもあります。
このように直線でのフラつきは、これらの運転手とは関係ない次元でのフラつきと、
運転手自らが行うハンドル操作により発生します。
何故フラつきを抑制するのが難しいか
先の車の特性や道路の凸凹によるフラつきは、フラつきを運転手が感知するころには完全に事後です。
言い換えると通りすぎてしまっています。
これは凸凹によりフラついたものは抑えることは出来ないということです。
まずは、フラフラするのを抑制するのが難しいのではなく、出来ないと認識することが大事ということです。
何故ハンドル操作がフラフラするか
運転手の行なったハンドル操作がフラフラしてしまうことがあるのは、2つの理由があります。
1つは先にあげた車の特性によるものです。
運転手が意図したハンドル操作は時間差をともない、遅れて効果が生じてきます。
ハンドルとタイヤ間のみならず、タイヤと路面間でも時間差が生じます。
もう1つは、先の理由を知らないことからくる、過剰反応によるものです。
時間差を考慮しないうえに、早急に結果を出したく結果を待たずして事前の操作への訂正を加えてしまいます。
例えば以下の様な場面があったとします。
- 曲がりたいだけハンドルを切ったつもりが思ったほど曲がらない
ここで次のような意図で操作を行います。
「曲がりたいだけハンドルを操作したつもりなのに思ったほど曲がらないので更にハンドル操作を加える」
そして、次回の同様な場面では、経験値を活かした次のような意図で操作を行ってしまいます。
「自分の感覚で曲がりたいだけハンドルを操作したのでは思ったほど曲がらないので自分の感覚よりも多めにハンドル操作を加える」
更に次回の同様な場面では
「新しく多めにハンドル切るように修正した自分の感覚で曲がりたいだけハンドルを操作する」
しかしその結果は
- 結果的に曲がりすぎてしまいハンドルを戻す羽目になった
となります。
このようにして運転手は致命的なダメージを受けます。
「私の感覚はあてにならない」
「私は運転がうまくない」
まずはこの勘違いを修復します。
この勘違いを修復しないうちは視点を遠くに向けてもフラつきは収まりません。
遠くに視点を移すのは行き先を認識するためであり、多少の効果があったとしてもフラつきの対処法ではありません。
勘違いの修復方法
勘違いの修復方法は、
まずは、外部要因によるフラつきは、今更修復できないと認識することです。
そして操作の結果が現れるまでには、時間が必要であると認識することです。
勘違いを認識した上でのハンドル操作は次の通り。
- 想定した操作を行ったら修正しないこと
修正できない外部要因によりふらついた場合はハンドル操作は行わないことです
自分のハンドル操作を信じることです。
まとめ
本編をまとめると次のようになります。
- 進行する道路を先読みし、走行ルートを決め、そのとおりにハンドルを操作する
ハンドル操作は遅れて効果が生じるので、その遅れを見積もりを入れて操作する。
このことは、様子を見ながら操作するのではなく最初にたてた計画通りにハンドル操作を行うことを意味しています。
そうして、運転手が事前に建てた計画に従い、自信を持って操作し、そしてその操作が成功裏に終わった暁には同乗者は運転手を信頼し、安心して運転を任せてくれることでしょう。
そんな先読みは、決めたルート通りの操作は行えないとお思いでしょう。
もちろん経験が必要です。
何でもかんでも甘い話はありません。
経験を積みましょう。
ただし、正しく経験を積むのです。
自分の建てた計画がどのような結果になるかを知ることが経験です。
途中で修正を加えた「間違いの経験」、「失敗の経験」、「下手くその烙印」は、
逆効果なので極力避ける事が正しく経験を積み気が付くと達人になる近道となります。
最後に付け加えます。
ハンドル操作が間に合わないとか、ぐるぐる回すと手が絡まってしまうとか。
ハンドルの握り方とかさばき方とかよりも、まず、ゆっくり走ることを優先しましょう。
急なハンドル操作が必要な場面は、実は停車して操作しても良いぐらいの場面だったりします。
メリハリを持って運転すれば、ゆっくり走っても、それが「下手くそ」の評価になることはありません。
身の程にあった運転をすることが一番だと懐います。
では。
【いやいや極める】お抱え運転手 ハンドル操作編














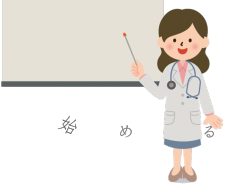
この記事へのコメントはありません。